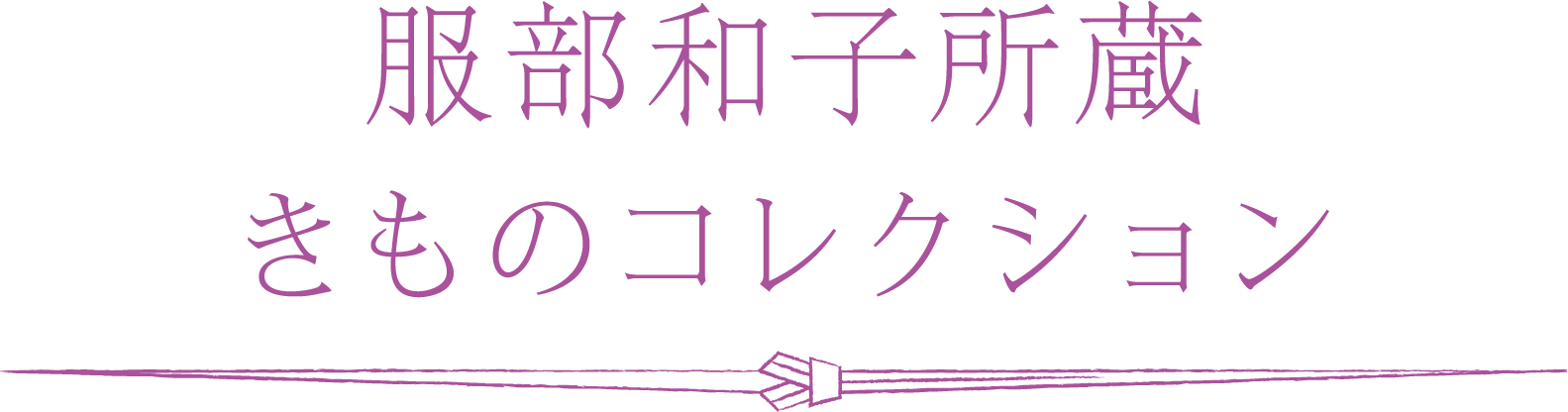『着つけをお教室で習う』。今では当たり前の文化になっていることは、私にとって本当に喜ばしいことなのです。さて、『日本で初めての着つけ教室』といいましてもピンとこない若い方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのお話をいたしましょう。
出会いはミスコンテスト
それは、まだ私が10代の頃。
ひょんなことから『ミス・西陣』に選んで頂き、その後、『ミス・きもの』『ミス・コットン』にも選ばれ、この時に『ミセス・きもの』に選ばれた女性と後々、一緒にきもの学院を始めることになります。
何かの運命だったのかもしれませんね。
開講当時、看板を出すか、トイレ掃除をするかを、2人でジャンケンで決めていたのも懐かしい思い出です。

着物と生きてきた
実家は悉皆屋(しっかいや)(友禅染、染み抜き、洗い張りなどをする)で、生まれた時から着物を着るのが当たり前という環境で育ちました。「着物は空気が入らんようにびしっとたたまなあかんえ」「着物を着たら、すぐに汗をとらなあかんえ」 。子どもの頃から着物通の母が毎日言っていたことも後になって役に立つようになっていきます。
ファッションモデル時代、最先端の美容家の方達から直接着物を着せていただく機会が増え、この着方は襟がが綺麗、この方が細っそり見える…など、技の奥義を見て、体で覚えこみました。

きっかけは、命拾い
モデルの仕事は、身体を壊すほどに多忙を極めていました。「もうたすからない」とお医者様に言われるまでに。
2年間に渡る病床で、もし命拾いをしたら、自分はどう生きていくのかを考えるようになりました。モデルの仕事は素晴らしかったけれど、何か他に社会に恩返しが出来るような仕事がしたいと。
ちょうどその時代は、洋服の生活へと変わっていくときで、着物を1人では着られない人が増えていく中、私はそのための技術だけはしっかりと身についていました。
その頃、着物というものは、母や祖母の着方を見て教わるもので、体系だったものがなく、小物の種類や帯の結び方など、細かな部分まで全てを教えてくれる場所はなかったんですね。

和子流の確立
日本中の人に着物が着られるようになってほしい!という夢を思い描くようになりました。そのためにはどうしたら簡単にきれいに着ることができるのか…。ての長さを決めたり、帯がシワにならずに結べる方法を考えたり、いろいろな方法に思いを巡らせていました。
着つけ教室がビジネスとして成り立つのかとの不安もありましたので、呉服屋の社長様にご相談に伺いましたところ、奥様とお嬢さんが私の着つけを体験してくださり、「あの着つけはよろしいですね、家内も覚えやすく楽に着られると言っています、やりなさい!」と、太鼓判を押してくださいました。その事が、私の背中を押してくれました。

開講、和子27歳
1964年(昭和39年10月1日)京都市左京区岡崎のいづのバレー団スタジオを借受着物着つけ教室を開講した。名称は『服部和子きもの学院』第一期生として30人を迎えた日本ではじめての着物教室誕生は、一般紙、地方紙、業界界紙、専門誌雑誌などで沢山報道されることになります。
着つけのテキストは、教本等あるわけもなく、プロセスを箇条書きにしたり、自分でイラストを描き、写真を撮り「これでわかるか?」と住み込みの方に試してもらいながら、手作りで作り上げていきました。
着物通の母は、着つけを教えるとは日本人に日本語を教えるようなもの着つけ教室を始めた時は、27歳にもなって結婚もせずそんなことをやり始めるなんて!と嘆いておりました(笑)。

新たな着物文化の誕生
全国で出張教室を開き、分校は100を超え、TVでの着つけの番組の放送後は大反響で、電話がなりやみませんでした。
着つけ教室を巣立っていった生徒の中にはそれぞれが独立してお教室を始める方も少なくありませんでした。
今日まで、着つけ教室が文化となり『きもの学院』という、新しい業種ができたことを誇りに思っています。
衣は人なり。
装いも内面も美しく、と今もかわらず常に願っております。

服部和子による講演等のご依頼はこちら
日本人の装いは、その時代背景によって、多くの変遷と
さまざまな美しさを表現してきました。
その意匠の美、 手技の美など見どころはつきません。もっとも魅力を感じるのは、
一枚のきものに託された、願いや想い、祈りを心で感じるときの楽しさです。
ご縁があって、私のもとに集まってきたきもの達。
生きたコレクションとしても、きもの振興に役立てて いきたいと思っております。
ここでは、代表的な数点をご紹介いたします。

十二単(復元)
平安中期のころの上層階級の女性の晴れ着です。
十二単と呼ばれるようになったのは江戸時代のことです。それ以前には唐衣裳(からぎぬ)装束(すがた)、または物具姿(もののぐすがた)といわれていました。
当時は階級制度が厳格に守られていた封建時代、当然着るものの色や柄にも定められたものがあり、唐衣の色にも禁色が決められて、赤・青・もえぎ色などは許しを得なければ着ることができませんでした。
![白緞子地仙境双鯉遊泳文様裲襠[江戸時代後期]](https://kimonomuseum.com/cms/wp-content/themes/kimono-cms/images/kodai_p003.jpg)
白緞子地仙境双鯉遊泳文様裲襠
[ 江戸時代後期 ]
新撰組隊長近藤勇が好んで通い遊んだ松扇太夫のものという裲襠(うちかけ)です。手刺繍のあでやかな菊花をぬって、寄り添いながらゆうゆうと泳ぎわたる対の真鯉と緋鯉。その真鯉の頭と背にある刺繍の黒い部分は人毛と伝えられています。さまざまな意味で、興味のつきない衣裳です。
![玉虫織老梅鴛鴦貝合図模様裲襠[江戸時代]](https://kimonomuseum.com/cms/wp-content/themes/kimono-cms/images/kodai_p005.jpg)
玉虫織老梅鴛鴦貝合図模様裲襠
[ 江戸時代 ]
水面にうつる紅白梅に群れ遊ぶ鴛鴦を可憐で豪華に刺繍で仕上げています。太夫は前で帯を結びますので、玉虫織の輝きが後姿をより華やかにしています。
裲襠(うちかけ)とは、着流しの重ね小袖の上に羽織って着ます。
![太夫掛下 下衣[江戸時代後期]](https://kimonomuseum.com/cms/wp-content/themes/kimono-cms/images/kodai_p004.jpg)
太夫掛下 下衣
[ 江戸時代後期 ]
太夫の打掛の下に着る掛下。鮮やかな紅色は、江戸時代多く栽培された紅花を原料にしていると思われます。
![太夫の下駄[江戸時代後期]](https://kimonomuseum.com/cms/wp-content/themes/kimono-cms/images/kodai_p007.jpg)
太夫の下駄
[ 江戸時代後期 ]
真冬であっても太夫は裸足。形よく、ちんまりとした白い足が履いたであろう、この三枚歯の塗り下駄は鯨尺で約五寸(十八センチ)の高さ。重さもかなりのものです。供を従え八文字と呼ばれる独特の歩き方で、みごとな太夫道中を繰り広げた昔日がしのばれます。
なお、本品にある松扇太夫の名前は島原随一の花魁の名として、これらの衣裳ともども昭和に至るまで 代々受け継がれてきました。
![黒一越縮緬地蓬莱山瑞祥扇面模様江戸褄[ 大正時代 ]](https://kimonomuseum.com/cms/wp-content/themes/kimono-cms/images/kodai_p006.jpg)
黒一越縮緬地蓬莱山瑞祥扇面模様江戸褄
[ 大正時代 ]
蓬莱山の吉祥文様が左右対称に染め出されている江戸褄で、裾の暈(ぼか)しはこの時代の特徴のひとつです。
江戸後期から流行しはじめた江戸褄は、大正期に入っていよいよ定着の度合いを深め、現在の黒留袖への流れとなります。なお蓬莱山とは中国に伝わる伝説で、東海にあって不老不死の仙人が住む霊山だとされています。わが国では富士山のことともいわれ、衣裳も文様だけではなく、祝い事の飾りなどにもよく見られます。
![紫一越縮緬地孔雀薔薇文様振袖[ 昭和時代前期 ]](https://kimonomuseum.com/cms/wp-content/themes/kimono-cms/images/kodai_p002.jpg)
紫一越縮緬地孔雀薔薇文様振袖
[ 昭和時代前期 ]
十三参りは子供の健やかな成長を願い、大人になるための知恵を授かる行事です。この時、女の子は初めて本身(大人の寸法)のきものを身にまといます。肩上げをして着ますが、その後大人になると縫い上げをはずします。
白孔雀と薔薇の模様をあしらった本品は、楚々とした中に薫り立つような華やかさが満ちあふれ、いかにも娘衣裳らしいものです。